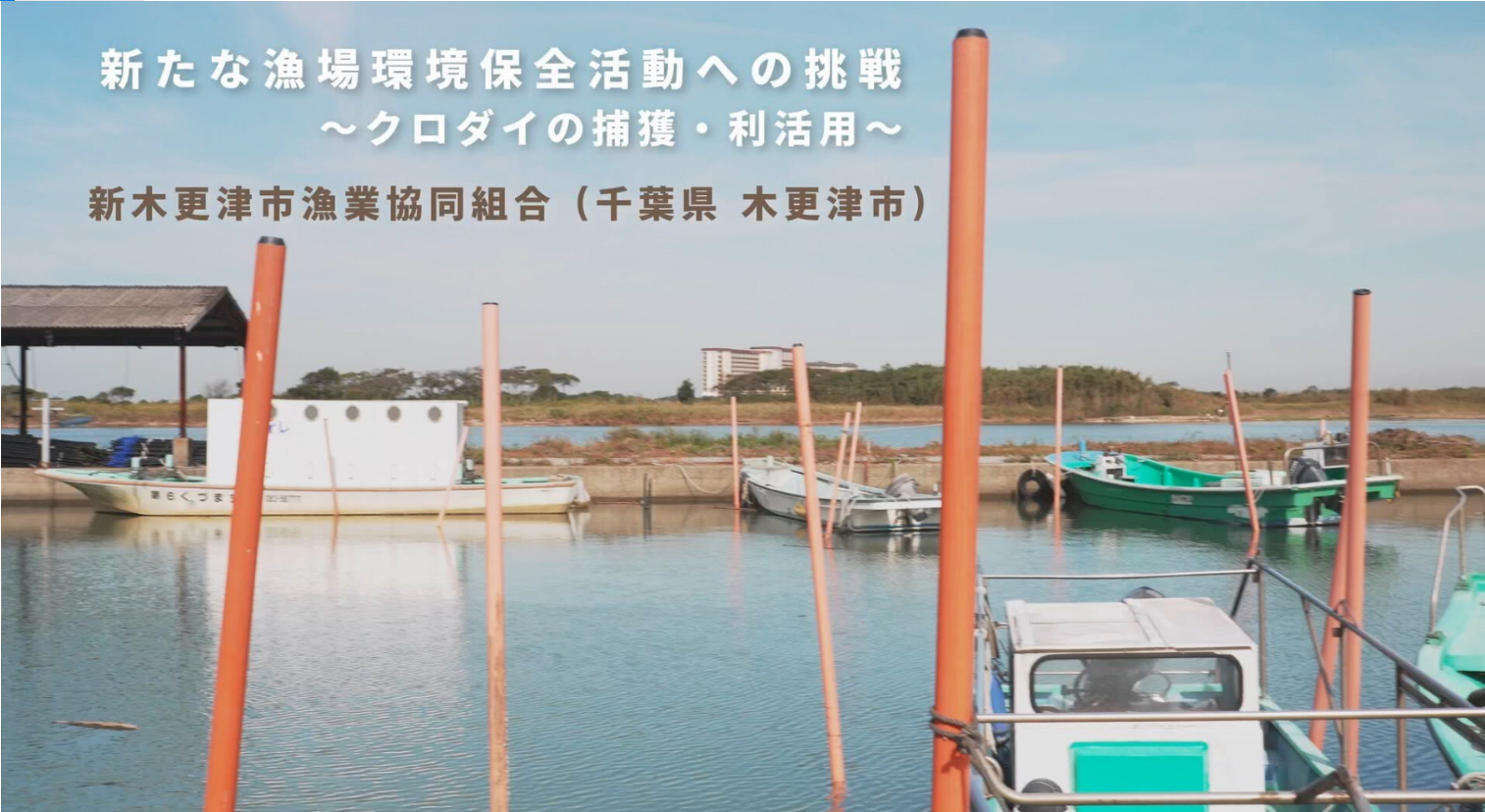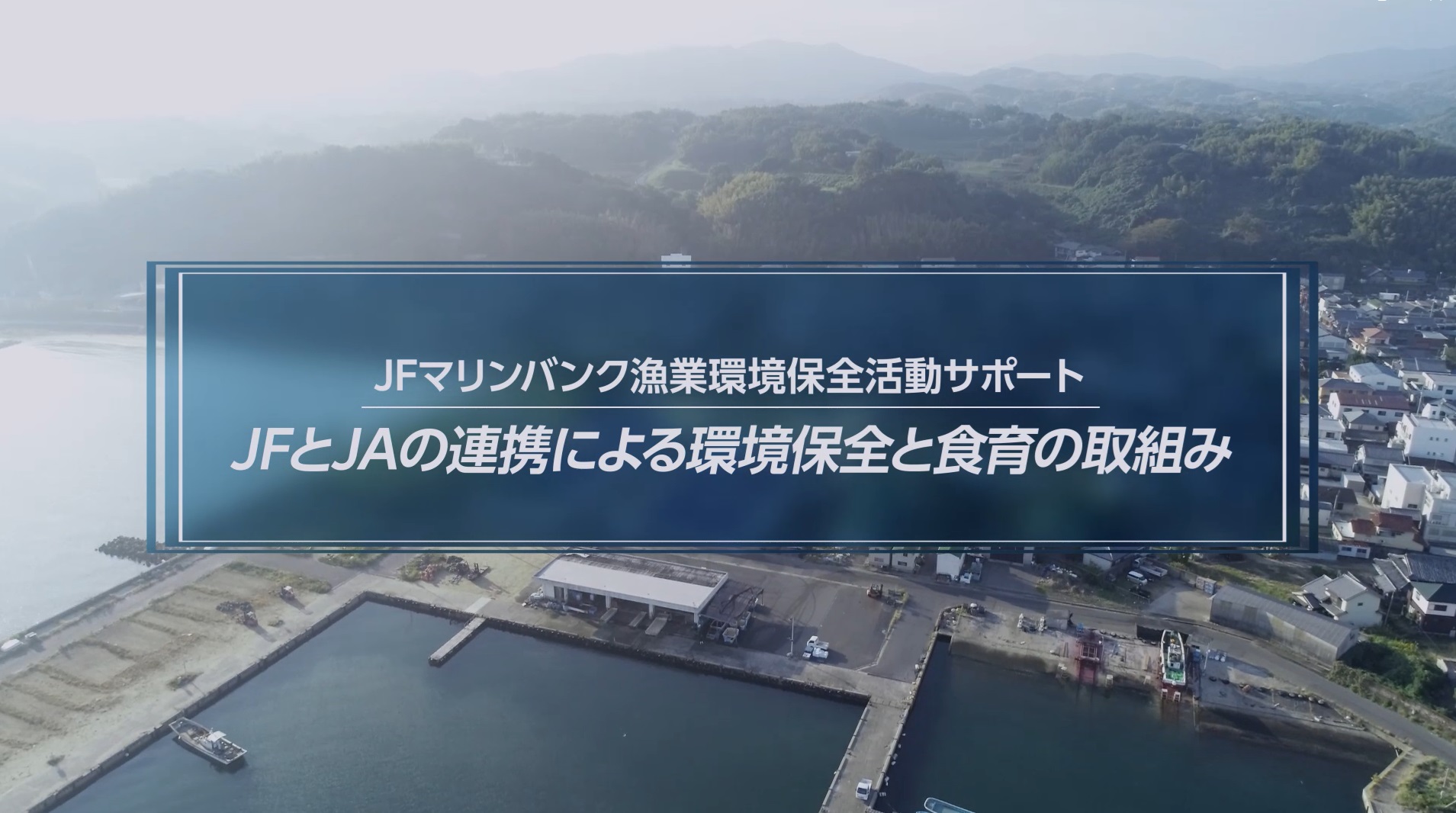ビジネス
聞いて、試して、やってみる。漁師たちの組織が変化の波を乗り越えられた理由
少子高齢化、過疎化や人手不足、あるいは天候変動による災害や国内市場の縮小、さらには産業構造の変化に、価値観や嗜好の多様化──。
「変化の激しい時代」と言われる現代において、日本企業の多くがこれからの時代をどう乗り切っていくか、手がかりをつかみあぐねている状況です。
大企業がベンチャー企業と手を組んで実験的な試みをするなど、新規事業開発を目論む企業も少しずつ増えています。
けれども当然ながら、新しいことをはじめるのは、容易ではありません。
「見込みのないことに予算はかけられない」「前例がないからわからない」といった意見で否定されたり、「これまでのやり方が変わってしまうのは不安だ」と社内から反発の声が上がるのもよくあることです。
そんななか、「変わりつづけること」で、変化の波を乗り越えてきた組織があります。愛媛県宇和島市にある遊子(ゆす)漁業協同組合(以下、遊子漁協)です。
自然を相手にする漁業では、天候不順や赤潮、災害など予期せぬ環境変化で苦境に立たされることはそう珍しくありません。遊子漁協はそういった困難をどう乗り越えてきたのでしょうか。
遊子漁協の試みは、ビジネスの世界で新たなことに挑戦しようとする人にとって、大きなヒントになりうるものでした。
巻き網漁、真珠養殖、魚類養殖......遊子漁協がたどった変遷

遊子漁協は愛媛県の西部に延びる三浦半島の北側にあります。リアス式海岸で入り組んだ内海は穏やかで、養殖用のいけすがいくつも連なります。



冷たい風が頬をなでる朝。漁協ではマダイの出荷準備がはじまっていました。いけすから水揚げされたマダイは、生きたまま各地の鮮魚市場へ運ばれます。

一方、その敷地内にある加工場「マリンコープゆす」では、マダイが鮮やかな手つきで捌かれていました。
マリンコープゆすには、魚の細胞を壊すことなく新鮮な状態で急速冷凍する「CAS(セルアライブシステム)」など、最新鋭の設備が整っていて、全国のみならず海外にまでその美味しさを届けています。
「漁協でここまでやってるのは、ほとんどないけんね。よく他の地域からも視察に来られるんよ」
そう話すのは、遊子漁業協同組合代表理事組合長の松岡真喜男(まつおか・まきお)さん。1978年に組合に入り、遊子の漁師たちを支えてきました。