ビジネス
「自分も他者も儲けて、海も守る」売れないローカル珍魚を売って漁業もする魚屋
鮮度管理徹底し魚価向上 設備充実、売り先も開拓
もうひとつは漁港からの「売りたい」に答えるケース。シーズンにもよりますが、特定の魚がたくさんとれて困っちゃうことが往往にしてあるんですね。しかも市場では価値がつかないような魚が。そういう相談を僕たちが受けて、飲食店さんに「こういう魚があるんですがメニューとして提供しませんか?」と提案して買ってもらうんですよ。
── 漁港が買って欲しい魚も積極的に買われるんですね。
はい。あと、僕たちは食品加工も請け負っているんです。買い取った魚を加工品として販売するんですが、獲れ過ぎて漁港が困ってしまうのを助けてあげることができるんです。
たとえば鹿児島県でよくとれるカタボシイワシっていう魚がいるんですが。小骨が多いから市場に好まれなくて、海上投棄されてたんですよ。

そこで僕たちはフィレを酢締めにして骨を軟らかくしたものをつくって販売しました。飲食店もそれならおいしく消費できる。いまでは回転寿司などで使ってもらっています。
ひたすら足で稼ぐ食一の営業方法
── 漁港と飲食店、双方に直接関係を持つからできることなんですね。そもそも、その関係づくりはどうやっているんでしょうか。
もうこれは地道な営業の一言につきますね。「ここで獲れる魚を買いたい」とお願いにいくんです。営業といっても、漁港の人たちと人間関係を築いていくというイメージ。どうしてもそこの魚が欲しくて、5年ほど通い続けてようやく取引できるようになった港もあります。
── 5年もですか......! 権利関係や上下関係も厳しい漁業の世界ですし、じっくり時間をかけて信頼を得ていくんですね。
そうですね。漁港ごとのパワーバランスも重要視していて、漁協に営業をかけることもあればトップに立つ漁師さんに話しにいくこともある。時には漁船に同乗して、現場のリアルを体感することも。客とはいえ、結局はよそ者です。抜け駆けや誰かの顔に泥を塗ることがないよう、筋を通すことだけは徹底しています。

地道な営業のおかげで、取引させてもらえる漁港も増え続けていますね。馴染みへの挨拶・新規開拓合わせて、年間で200カ所以上の漁港に出向きます。産直の魚屋では日本でいちばん漁港に行っているんじゃないかな。
── すごい!
取引成立に時間がかかる漁港と契約を結べた時は嬉しいです。「どうしてもここの魚を使いたいってお店があるんです! なんとかなりませんか!」って懇願して、じゃあ今回だけなら......とオッケーもらったら、「なんだ~、いけるじゃないですか! 次もお願いします!」ってシレッと次回の取引もお願いしちゃう(笑)。
── ははは(笑)。飲食店も同様に足で稼いでいる感じですか?
いまでは口コミや、たとえば食一で魚を卸していたお店で働いていた人が独立して......という形でお客さんも増えているんですが、軌道に乗るまでは直接の営業が主でしたね。
「今日はこのエリア!」って決めて飲食店を回りまくってました。ママチャリで(笑)。
── 地道ですね。
僕、独立にあたって大学を休学していたんですが、その間に新聞契約の訪問バイトをしていて、全国だったか関西だったかは忘れちゃったんですが、学生ターゲットの営業成績でトップ10に入っていたんです。差別化しにくい新聞という媒体をどう買わせるか、営業トークから服装、喋り方に至るまで、ノートにポイントや反省点を書き起こして研究していたんです。その経験は食一を立ち上げてからもすごく活きていますね。。
── バイトでそこまでみっちりやるとは! しかも大学を休学していた......?
波乱万丈さは"激レアさん"!? 「進学させられた」同志社大学が起業のスタートに
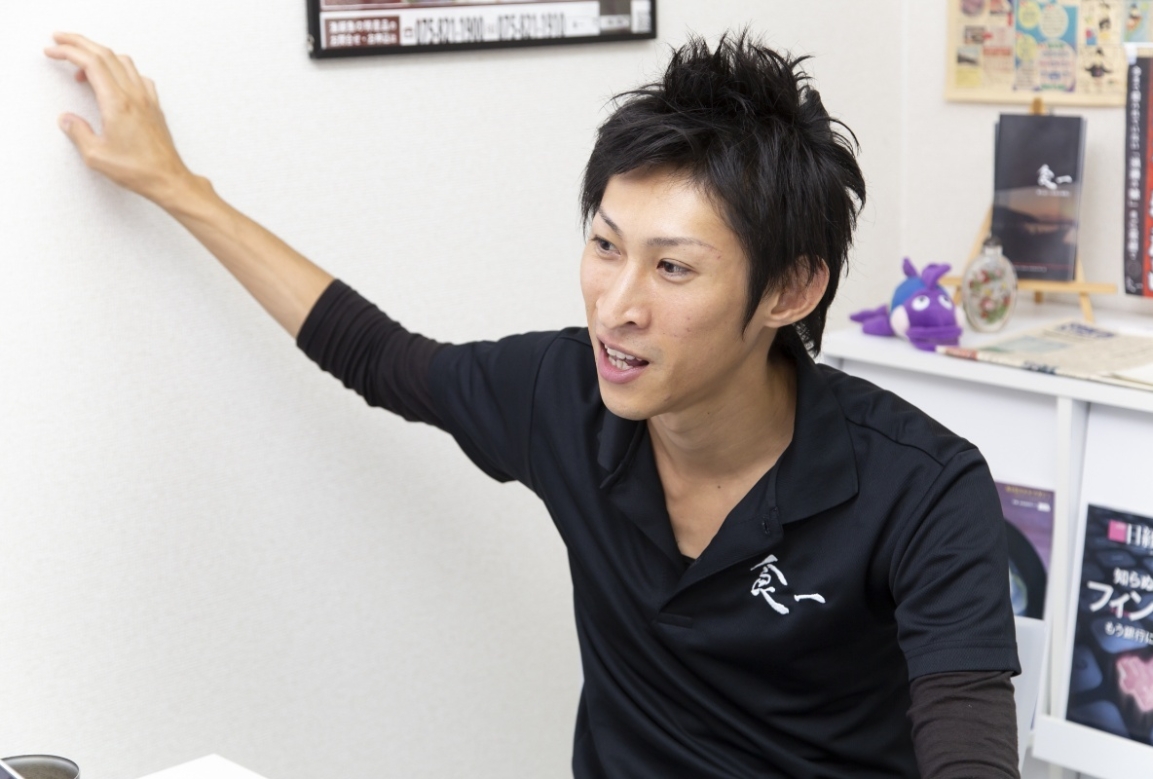
── 田中さんは、そもそもどういう経緯で食一を立ち上げられたんでしょう?
僕は佐賀県の伊万里出身で、実家は長崎県の松浦で、130年くらい続く仲卸専門の魚屋なんです。僕はその次男。高校卒業後はどこかに就職をして経験を積んで、ゆくゆくは兄と一緒に家業を継ぐものだと思って育ちました。
── でも田中さん、大学進学されていたんですよね?
そうなんです。同志社大学に入学しまして。
── 同志社!? 関西有数の高偏差値大学に何故......。
無理やり進学させられたんですよ! ある日先生から「田中、ドウシシャに行かないか」って呼び出されたんです。本当にアホな話なんですけど、僕は同志社大学の名前を知らなくて。同名の宝石メーカーがあって、就職への斡旋をしてくれるんだとばかり思っていたんです。
